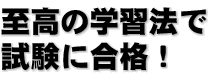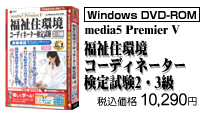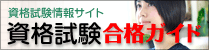福祉住環境コーディネーター検定試験を目指す人を応援するページ |
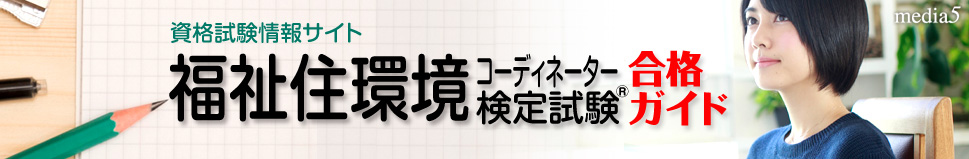
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉住環境コーディネーターとは |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高齢者(65歳以上)は今や、過去最高の3,190万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)は、25%と過去最高を示しております。 さらに20年後の平成47年(2035)には、総人口の3人に1人(33%)となり、その後もこの傾向は続き、47年後の平成72年(2060)には40%に達し、国民の2.5人に1人は65歳以上の高齢者となる社会が予測されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方、平均寿命は、平成24年(2012)、男性79.9歳 女性86.4歳で、平成72年(2060)には、男性84.2歳 女性90.9歳と予測されています。 その中で、高齢者を取りまく環境は ・高齢者(65歳以上)世帯は全体の4割、うち「1人」「夫婦のみ」世帯が過半数 ・子供との同居は減少 ・1人暮らし高齢者の増加傾向で、平成22年(2010)高齢者人口の男性11%、女性20%となっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 このような背景において、 このような背景において、 高齢者、障害者の方に関する、医療、保健、福祉から、建築、住宅構造、福祉用具までの幅広い知識をもち、それぞれの分野の専門家と連携し、個々の身体状況をはじめ、さまざまな生活上のニーズに応じた最適な住宅環境を提供する役割を担っていくのが【福祉住環境コーディネーター】です。 検定試験は東京商工会議所の主催で、1999年5月に3級、2000年に2級がスタートし、2002年には、1級試験も始まりました。 ※工務店・リフォーム会社と医療・福祉の専門家との、それぞれの専門性を生かしながら、本人の必要とする、最適環境を提供していくのが、まさに福祉住環境コーディネーターの社会から求められる重要なポジションであると言えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 内閣府が2014年公開した「高齢社会白書」によると、「分の体が衰えた時に済みたい家」で自宅をリフォーム(改装)して住み続けたいという人が増えています。 内閣府が2014年公開した「高齢社会白書」によると、「分の体が衰えた時に済みたい家」で自宅をリフォーム(改装)して住み続けたいという人が増えています。 「高齢になっても、障害があっても、住みなれたところで暮らしたい、・・・」という人が60歳以上対象で、66.4%います。 ただ、自分の体が弱ったり、何らかの障害がおきたりした時、自宅内、外出先でのいろいろなリスクがあるのは、事実です。その中で、高齢者による事故は、その7割強ほどが住宅内と言われています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このように、高齢者が家庭内で起こした事故で骨折、寝たきりになるなど、入院を余儀なくされる事例が若年層の2倍を示しています。 ・高齢者、障害者が自宅で安全に、便利に暮らせる ・高齢者、障害者が自立した日常生活を送り、活動への意欲を高める事ができる・・など ↓ 住環境整備によって 高齢者、障害者本人のみならず、介護者の負担軽減もできます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉住環境コーディネーターの主な仕事の内容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉住環境コーディネーターは医療、保険、福祉、建築など幅広いジャンルの知識を身につけ、実際に住環境整備を進める中では、本人のヒアリングは勿論ですが各専門家との折衝、調整が大変重要となってきます。 その上で、最終的には、福祉住環境コーディネーター自らが考え、利用者本人の「使いやすさ、その人らしさ」を尊重する姿勢が求められます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祉住環境コーディネーターの活動場所は主に、次のような分野があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| など、多岐にわたりますが、大切な事は、自ら進むべき分野で、この知識をどう生かすかを、思考することで、あらゆる可能性が生まれる、ということです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉住環境コーディネーターをめざすには |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2016年受験者の内訳】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【2016年度 試験結果】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祉住環境コーディネーター検定試験の内容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●試験概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●出題範囲 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●受験日程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験実施地域・会場 東京商工会議所および各地の商工会議所が主催 【地域】3・2級は全国220か所程、1級は全国15か所程 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格から実務に就くまで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)建築・福祉・医療の知識・経験がない人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓(福祉住環境コーディネーター3級取得)必須ではない 建築・福祉・医療の知識を学ぶ ↓ 福祉住環境コーディネーター2級取得 ↓ ・企業・団体・自治体などに勤務し、住環境整備にかかわる ・現職業の中で、住環境整備にかかわる ・住環境整備にかかわる職場への転職 ・・・など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)建築・福祉・医療の専門知識をもち、すでにこの分野で働いている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓(福祉住環境コーディネーター3級取得)必須ではない 福祉住環境コーディネーター2級取得 ↓ ・現職業の中で、住環境整備にかかわる ・住環境整備にかかわる職場への転職・・・など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらに福祉住環境コーディネーター1級を取得し、地域のまちづくり参画するなど、より広い視点で、住環境整備に関わることが可能となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“福祉住環境コーディネーター検定試験(R)”は東京商工会議所の登録商標です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2級頻出用語 | |||
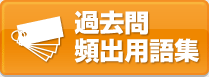 |
|||
| 3級頻出用語 | |||
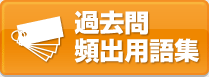 |
|||
|
|||
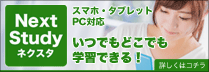 |
|||