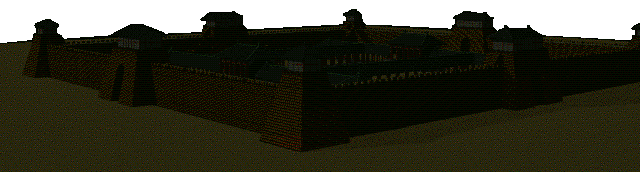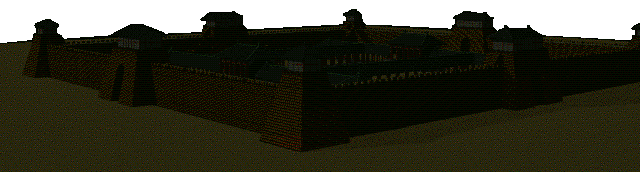|
孫子曰いわく、凡そ衆を治むること寡を治むるが如くなるは、分数是れなり。
衆を闘わしむること寡を闘わしむるが如くなるは、形名是れなり。
三軍の衆、必らず敵に受けて敗なからしむべき者は、奇正是れなり。
兵の加うる所、段を以て卵に投ずるが如くなる者は、虚実是れなり。
|
|
大軍を治めることを小隊を治めるようにするには、人数を分けなければならない。
大軍を小隊のように思うように戦わせるには、形が重要である。
大軍を敵に当たらせ、絶対負けないのは、奇襲と正攻の兵法である。
石で卵を割るように攻撃するのが虚実の兵法である。
|
|

|
|
|
凡そ戦いは、正を以て合い、奇を以て勝つ。
故に善く奇を出だす者は、窮まり無きこと天地の如く、竭きざること江河の如し。
終わりて復た始まるは、日月是れなり。死して復生ずるは、四時是れなり。
|
|
戦いは正攻法をもって敵と対峙し、奇襲でこれを破る。
従って奇襲を得意とする司令官は、天地のように果てがない。
大河のように尽きることがない。
没して出る日月のように、死んだと思うとまた生まれてきて、春夏秋冬の運行のようである。
|
|

|
|
|
声は五に過ぎざるも、五声の変は勝げて聴くべからざるなり。
色は五に過ぎざるも、五色の変は勝げて観るべからざるなり。
味は五に過ぎざるも、五味の変は勝げて嘗むべからざるなり。
戦勢は奇正に過ぎざるも、奇正の変は勝げて窮むべからざるなり。
奇正の相い生ずることは、循環の端なきが如し。孰か能くこれを窮めんや。
|
|
音階も色も味も五種類あるが、それらを組み合わせると無限の変化が生まれる。
戦いも正攻法と奇襲の二つあるが、この二つの戦術の変化は限りなくあり、極め尽くせない。
|
|

|
|
|
激水の疾くして石を漂すに至る者は勢なり。
鷙鳥の撃ちて毀折に至る者は節なり。
是の故に善く戦う者は、其の勢は険にして其の節は短なり。
勢は弩を引くが如く、節は機を発するが如し。
|
|
激流が石を舞い揚げる勢いが「勢」である。
鷲がくちばしで一撃のもとに真二つにしてしまうのが「節」である。
ゆえにいくさ上手の人は勢い険しく、節は短い。
勢いは弓を引くように、節は機を発するようにする。
|
|

|
|
|
乱は治に生じ、怯は勇に生じ、弱は強に生ず。
治乱は数なり、
勇怯は勢なり、
強弱は形なり。
|
|
乱れは治まりの中から生じ、臆病は勇敢の中から生まれる。
弱は強より生まれる。
治乱は統制力の問題である。
勇怯は勢いの問題で、
強弱は軍形によるものだ。
|
|

|
|
|
故に善く敵を動かす者は これに形すれば敵必らずこれに従い、
これに予うれば敵必らずこれを取る。
利を以てこれを動かし、詐を以てこれを待つ。
|
|
敵を自由に操る指令官はイメージする体勢に敵は必ず動き、
餌を放ればこれを必ずとる。
利によって敵を誘っておき、一方で敵を壊滅しようと待ち構える。
|
|

|
|
|
故に善く戰う者は、これを勢に求めて人に責めず、故に能く人を択びて勢に任ぜしむ。
勢に任ずる者は、其の人を戦わしむるや木石を転ずるが如し。
木石の性は、安ければ則ち静かに、危うければ則ち動き、方なれば則ち止まり、円なれば則ち行く。
故に善く人を戦わしむるの勢い、円石を千仞の山に転ずるが如くなる者は、勢なり
|
|
だから戦さ上手は組織で動き、個人に依存せず、適材適所で勢いの形に乗せられる。
勢いに乗れば、木石が転がるように兵は戦う。
木石の性質は平らな所では静かにしているが、急な斜面になれば動く。四角なら止まり、丸ければ動く。
だから丸い石を千仭の谷の谷に転がるように、人を戦わすことが勢いである。
|
|

|
|